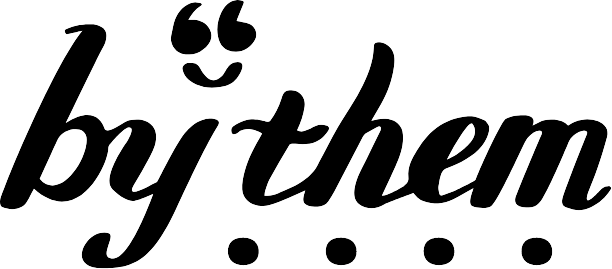こんにちは。無料メルマガ「速効!!よい子」で、真剣に子育てを考えている人に教えたい、子どもをよい子にする方法をお届けしている増田浩二です。
きょうは私のメルマガから、「読書が好きになるための2つの環境」について事例をもとにお話しします。
読書が好きになるための環境
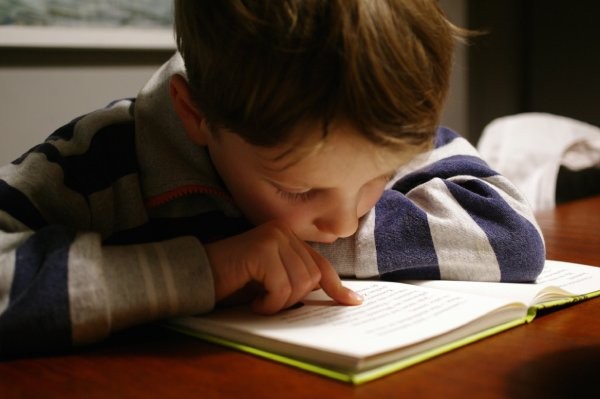
image by:Unsplash
以前見たテレビ番組で、ピアニストの清塚信也さんがお母様の話をしていました。
清塚さんのお母様は、クラシックがお好きで、清塚さんに音楽の道を歩んでほしいと思っていたそう。そのため、幼いころから音楽の教育を受けていたと言います。
そういった環境の元に生まれたので、音楽の道に進むのは自然なことだったということです。
清塚さんに限らず、ピアニストなど音楽家のインタビュー記事を読むと、親がピアノの先生だったという方も多いように感じます。
これまでにもお話ししてきましたが、親が好きなものや人生を通して夢中になっているものを、子どもは自然と好きになります。
たとえ最終的に好きになることはなくても、関心を持ったり、自然に技術を身につけたりするのです。
そのため、親が読書好きで読書の習慣があれば、子どもも自然と本に触れるようになります。
悩ましいのは、親はそれほど読書の習慣があるというわけではないけれど、読書は大事だから子どもには読書好きになってほしいという場合です。
清塚さんのお母様はピアノの先生ではなく、逆に音楽が苦手な方だったそう。
でも、清塚さんをピアニストにするために、徹底的にピアノを練習させたそうで、6年生のころには「自分はピアニストにならなければほかに生きていく方法がない」と清塚さんが思い込むほど、ピアノ以外のことをやらせてもらえなかったようです。
この話を聞くと、親が特に本をたくさん読んでいなくても、子どもを読書好きにさせる方法はありそうです。しかし、かといって、読書のスパルタ教育は、なかなか考えられません。
読者が好きな子の2つの共通点
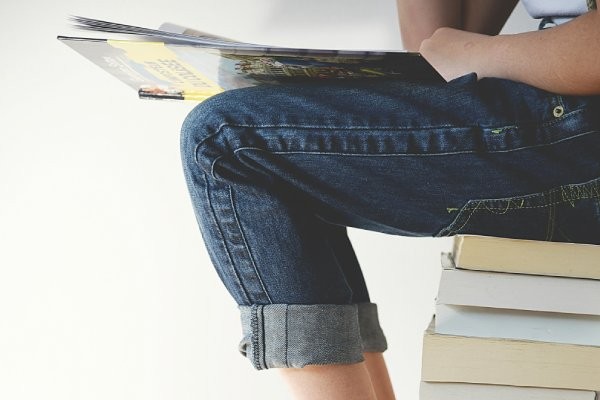
image by:Unsplash
読書好きな子たちの話を聞くと、彼らが育った環境には2つの共通点があるようです。
- 本が近くにある
- 本のことを共有できる人が近くにいる
この2つのことを満たしてやれば、子どもは読書好きになりそうです。
1を実践するのは簡単ですね。子どもが生まれたら、子どもの周りにたくさん本を置いておけばいいのです。
私の2歳になったばかりの孫は、まだ文字は読めませんが、自ら絵本を開いて、それを指さしながら何か言ったり、歌ったりしています。
2歳までの子どもは、身の回りにあるもの、すべてに触れてみたいのです。
1に比べて、2の方は難しく思えるでしょうか。2は、2つの時期にわかれます。
子どもがまだ十分に字が読めない期間は、一緒に声を出して読んでくれる人が必要です。よく言われる「読み聞かせ」の時期です。
子どもが自分で読めるようになったら、本の感想を言い合える人が必要です。
読み聞かせが重要だとは多くの人が言っていますが、次の時期に感想を言い合える人が必要だということを言う人は、案外少ないかもしれません。
しかし、10歳までにこういう人が身近にいるかどうかは、とても重要です。
小学校低学年の子が読む本なら大人は簡単に読めるので、読書がそんなに好きではない親も、子どもと「感想を言い合える人」に、簡単になれます。
周りに本を置く、読み聞かせをする、感想を言い合う。
親が、読書がそれほど好きでないとしても、人生100年のうち10年だけ無理してこれができれば、お子さんは読書好きになれるはず。
読書好きの子は、いざというとき、底力を発揮しますよ。
- image by:Unsplash
- ※掲載時の情報です。内容は変更になる可能性があります。
- ※一部内容を修正しました(2025/5/12)。
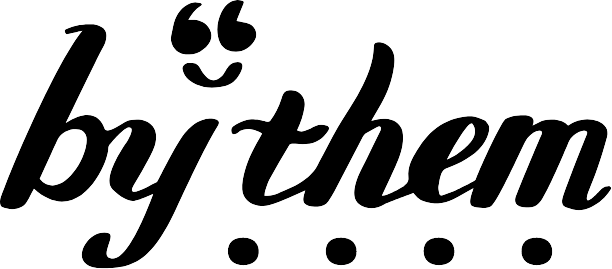

 0 件
0 件