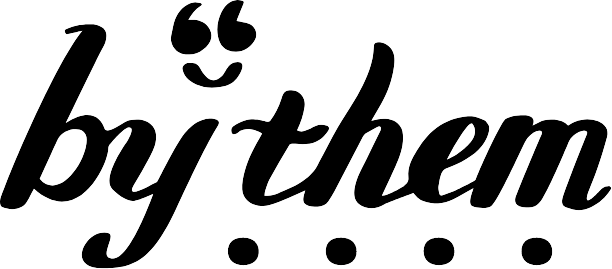こんばんは、ひとみしょうです。
「人に気をつかいすぎて、疲れてしまう」そんな経験、ありませんか?
誰かの機嫌を気にして、場の空気を悪くしないようにと笑ってみせる。
本当は断りたいのに「いいよ」と言ってしまう。
その優しさの裏で、心のどこかが少しずつ削れていくように感じることがあります。
“気をつかう”という優しさの矛盾

image by:Unsplash
「気をつかうこと」は、日本の文化では美徳とされています。相手を思いやる心、場を調和させる心。それは確かに、社会をなめらかにしてくれる大切な力です。
けれど、気をつかうあまりに自分を責めてしまうとき、その“やさしさ”は静かに自分を苦しめる刃に変わります。
「断ったら悪い人になる気がする」「自分が我慢すればうまくいく」――そんな思考の中で、私たちは知らず知らずのうちに、“自分の気持ち”を置き去りにしてしまうのです。
哲学に見る「やさしさ」の構造

image by:Unsplash
キルケゴールは、「他者との関係の中で生きる自己」を問い続けた哲学者です。彼は言いました。
「人は他者の期待の中に自分を見失うとき、絶望する。」
この言葉は、“気をつかいすぎる人”そのものを指しています。
他人の目に映る“よい自分”であろうとするほど、本来の“生きた自己”が遠ざかっていくのです。
キルケゴールの言う“本当のやさしさ”とは、相手に尽くすことではなく、自分に誠実であることです。
自分の心に起こっている感情を正直に見つめ、「私は本当はどう感じているのか」を受け止める。
そこから初めて、他者に向けるやさしさが生まれます。
なぜなら、自分を偽って差し出すやさしさは、やがて苦しみを伴い、相手との関係さえも不自然にしてしまうからです。
自分に誠実であること――それは、わがままではなく、人と真に向き合うための第一歩なのです。
“気づかい”を“思いやり”に変えるには

image by:Unsplash
気をつかうことと、思いやることの違いは、「自分を犠牲にしているかどうか」にあります。
思いやりとは、相手を尊重しつつ、自分も尊重すること。そこには“対等さ”があります。
たとえば、「あなたの気持ちはわかるけれど、私はこう感じている」と言える勇気。それが本当の意味での「やさしさ」です。
それはときに、相手を傷つけることもあるかもしれません。
でも、表面的なやさしさではなく、“関係を本気で生きようとする誠実さ”がそこにあるのです。
やさしさは「境界」から始まる

image by:Shutterstock.com
やさしさは、相手との境界を曖昧にすることではなく、むしろ“線を引く勇気”から生まれます。
「これ以上は無理」と言えること。「今日は疲れているから休みたい」と言えること。
その小さな線が、自分の心を守り、やがて他人との健やかな関係を育てていきます。
哲学とは、そんな線を引く“心の思考法”でもあるのです。
他者との関係におけるやさしさを、もう一度「自分の目」で見直してみてください。
おわりに
本当のやさしさとは、相手のために自分を消すことではなく、自分の心を大切にしながら、他者に向き合うこと。
誰かの気持ちを思いやりながら、同時に「自分を生きる」。そこにこそ、人間らしい美しさがあります。
「やさしさ」は、他人を癒す力であると同時に、自分を取り戻す力でもあるのです。
- image by:Unsplash
- ※掲載時の情報です。内容は変更になる可能性があります。
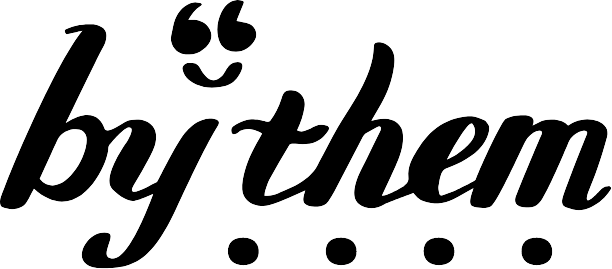

 0 件
0 件