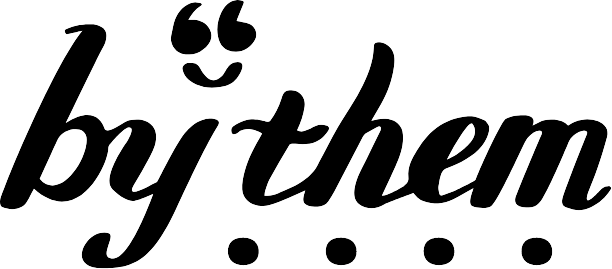神戸メンタルサービスの平です。ヴィジョン心理学創始者のチャック・スペザーノ博士に師事。プロセスを重視した本格的なグループ・セラピーを開講し、セラピストとして働いてきました。
令和の現在は「大人になりきれない」とか「大人になるのに抵抗がある」という子どもたちが増えていると言われています。
一方、昭和の子どもの多くは「早く大人になりたい」と思っていたようです。
なぜなら、なにかとガマンさせられることが多く、大人に対して理不尽な思いをもつことが多かったから。そして、子どもはガマンさせられているのに、大人たちはお酒を飲んだり楽しそうに見えるので、「ガマンしたり、支配されたりという状況から早く脱出したい!」ということで、自分も早く大人になりたいと思ったりしたのですね。
そんな昭和は遠い昔で、現在は非常に過保護な時代へと変化しています。
子どもにとっては居心地がよく、その子どもの目から、大人たちはガマンや辛抱ばかりしているように見えるようです。ですから、「ガマンばかりで楽しそうに見えない大人にはなりたくない」と思ったりするのですね。
「ピーターパン・シンドローム」と「ウェンディ・シンドローム」

image by:Unsplash
1983年、一躍脚光を浴びたのが“ピーターパン・シンドローム”という言葉でした。アメリカの心理学者ダン・カイリーの同名の著作によるものです。
ピーターパン・シンドロームは、大人になることや成長することを嫌い、永遠に子どものままでいたいという心理を表します。
そして、その傾向のある人は、身内や仲間に対しては反抗的であったり、わがままな態度をとることが多いと言われています。
一方、対外的な人間関係を築くことを苦手としており、社会適応のしにくい子どもであることが多いようです。
彼らは「大人になるのはいまの自分には到底無理で、過酷なミッションや修業を自分に課さないかぎり、あの人たちのようにはなれないだろう」などと自分を過小評価し、大人になることが困難だと感じているようです。
さらに「大人になれないこんな自分になっちゃったのは、○○が悪いからだ」と、自分ではなく親や学校や社会などのせいにすることで、罪悪感を遠ざけようとしています。
彼らはピーターパンのわがままを許し、甘やかしてくれる女性であるウェンディのような存在を表面的には求めます。たとえば、甘やかしてくれる母親の庇護のもとで、わがままを言っているようなパターンであるわけです。
ところが、男女関係となると、彼らは面倒見のいいウェンディではなくティンカーベルというクールな女性のほうに魅力を感じます。
ティンカーベルは自立し、しっかりとした女性で、ピーターパンである彼らは「いまの自分の世界を脱出するには、力強い自立の女性が必要だ」と感じているのです。
ちなみに、“ピーターパン・シンドローム”に対し、“ウェンディ・シンドローム”という言葉も存在します。前述のように、ウェンディはピーターパンを甘やかし、わがままを聞き、面倒を見つづける女性です。
つまり、“ウェンディ・シンドローム”とは、「自分のことを後回しにし、愛する男性を優先する」とともに、「嫌われることを怖れ、たえず相手に自分を合わせたり、自分を殺してしまう」というパターンをさします。
この傾向があるとピーターパンをどんどん甘やかしてしまい、 “イネーブラー”の状態に陥ってしまうこともあるようです。心理学的で言うところの“イネーブラー”は、アルコール依存症の患者が欲しがるままにアルコールを与えてしまう人を指します。
そこまでピーターパンのわがままを許し、面倒を見たウェンディですが、ピーターパンは自立的なティンカーベルに惹かれます。ウェンディとしては、これだけ尽くして捨てられるわけですから、やっていられませんよね。
なお、“ピーターパン・シンドローム”にあてはまる人の多くは、「自分で自分を変えていける」と感じることができません。「だれかが私を変えてくれなければ、私は変わることはできない」という信念をもっており、この信念こそがその人が本来もつ力を奪っているようなのです。
さらに「自分を変えてくれなかっただれか」への文句と不満が止まらず、たえず「自分の不幸は○○のせい」にしています。それによって、自分には自分を変える力がないという信念がますます強化されてしまいます。
- image by:Unsplash
- ※掲載時の情報です。内容は変更になる可能性があります。
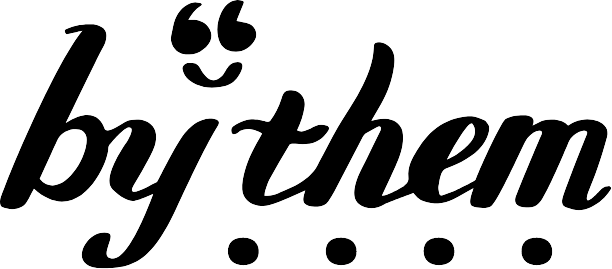

 2 件
2 件