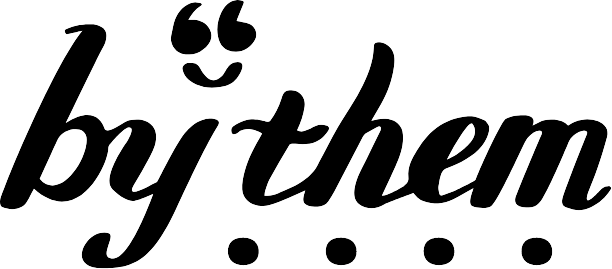こんにちは、太治です。さて、今回のテーマは「睡眠」です。
メンタルを安定させるためには、睡眠がとても大切です。寝不足の状態だと、些細なことでイライラしたり、頭が回らないなど、誰もが経験したことがあるでしょう。
メンタルクリニックでは、まずは抗うつ薬を出すという認識を持っている方が多いのではないかと思っていますが、実は「睡眠導入剤」だけ処方されることもよくあります。
というのが、そこまで深刻な症状でない場合、眠れさえすれば、メンタル症状が改善することがあるのです。
ちなみに抗うつ薬は、効果が出るまで1カ月程度かかってしまったり、薬の相性に左右されるため、そもそも効果が出ない可能性すらあります。そのため、睡眠導入剤が薬の第一選択肢になります。
とはいえ睡眠を大事にしようといわれても、メンタルを崩してしまうと、例外なく眠れなくなります。やはり崩してしまう前に、対策を打つことが重要になってきます。
睡眠に関してはビジネスチャンスのような風潮で、書籍から動画まで、さまざまな情報であふれかえっています。
そこで私自身が実際に試し、効果があり、かつ継続できたものを今回紹介していきたいと思います。
今から実践できる睡眠不足解消法3選
湯船につかる

image by:Unsplash
深い睡眠を得るためには「深部体温」という内臓温度を1度下げる方法が良いと言われています。結論、お風呂に入れば深部体温を下げることができます。
入浴すると体全体が温まり体温が約1℃上昇します。入浴後は、血管が開いているため熱が放散されやすく、結果として体温が下がっていくという仕組みです。
温度が高すぎると神経が高ぶってしまうので、38~40℃程度のお湯に浸かることが推奨されます。
なお、じっくり体を温める時間が必要なので、シャワーで深部体温を下げるのは難しいと言われています。
もちろん全く効果がないわけではないのですが、シャワー派の方も、湯船につかる生活をオススメします。
私はいろいろな入浴剤を試すのが好きなので、自然と週5で入っています。「ちょっと楽しい」を取り入れて、湯船につかる習慣を作ってみましょう。
マインドフルネスを実践する

image by:Unsplash
名前だけは聞いたことがある人もいるかと思います。副交感神経を優位にすることで、リラックス効果を高めることができます。
「呼吸瞑想」「ボディスキャン瞑想」「歩く瞑想」など、さまざまな種類がありますが、寝る前にオススメなのは「呼吸瞑想」です。
私が試しているのは「4・7・8呼吸法」というもので、4秒で吸って、7秒止め、8秒で吐く方法です。
5~10分で始めてみて、無理なく継続できるやり方を探してください。
また、ひとりでやるのは難しいのでYouTubeを使うのもよいです。「10分 マインドフルネス」などの検索ワードで、いくらでも動画がヒットします。
誘導音声の声質、BGM有無、スピード感がしっくりくるものではないときっと次の日にやらなくなるので、ぜひよいものを見つけてください。
スマートフォンを触らない

image by:Unsplash
スマートフォンは太陽光と同じで、ブルーライトを出しています。冒頭に記載していた、太陽光を浴びることで「セロトニン」が作られます。
セロトニンが作られるとリラックスするどころか、活動エネルギーが高まり、むしろ目が覚めてしまいます。手元に太陽がある状態で、眠れるはずがありません。
スマートフォンを断ち切る方法は、アイデア勝負です。
スマホの電源を切る、手の届かない場所に置いておく、アプリを制限する管理アプリを使ってみるなど、いくらでも方法があります。
ちなみに…偉そうに書いている私は、寝る直前までスマホを見てしまっています(笑)。
私が編み出した方法は、画面の明るさを限界まで下げて、ブルーライトカット機能をオンにすることです(気休めにしかなっていない気はしていますが)。
睡眠に限らず、万人に共通した正解はありません。上手くいったら続けてみる、上手くいかなければ変える。
いわゆるPDCAサイクルを回すことで、自分の正解が見えてきます。
睡眠リズムをキープする

image by:Unsplash
仕事の疲れや解放感から、土日は長く寝てしまいますよね。今はそうでもないですが、昔は9:00過ぎぐらいまで寝ていました。
「サザエさん症候群」「ブルーマンデー」など負の塊のような言葉を目にすることがありますが、睡眠リズムの崩れは、その原因のひとつになっていると私は思っています。
寝る時間が変わってしまっても、起きる時間を変えないことがカギです。どうしても眠気が取れない場合は、昼寝をすることもオススメです。
昼寝に関しては、一般的に15~30分が理想だと言われていますが、私の場合、時間が気になってしまうので1時間程度寝ていることがあります。
もちろん医学的に正しいという基準で動くのもよいですが、自分に当てはまるかどうかは、別問題と思うところがあります。
スッキリ感を目安に、睡眠リズムが崩れなければOKという気軽な気持ちで、うまく昼寝を取り入れてみてください。
- image by:Unsplash
- ※掲載時の情報です。内容は変更になる可能性があります。
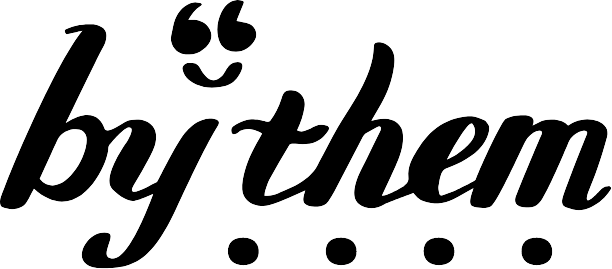

 19 件
19 件