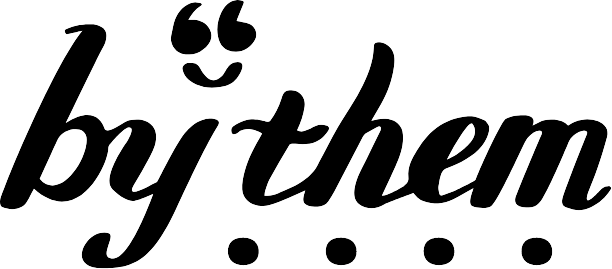そろそろ夏休みが近づいてきました。「今年の自由研究はどうしよう…?」と頭を悩ませている人も多いですよね。
そこで、今回は小学生におすすめのおもしろい自由研究アイデアを10個紹介します!ぜひ夏休みの自由研究の参考にしてみてくださいね。
リサイクルマーク集め

image by:Shutterstock
1つ目のアイデアは、リサイクルマーク集めです。
商品につけられているマークを切り取り、商品名とともに紙にまとめます。
それからどのような商品だったのか、どんなリサイクル方法がされるのかをまとめていくという自由研究です。
自分の身の回りのものにどんなリサイクルマークがついているのかを調べるのはもちろん、小学校でよく使う品にどんなリサイクルマークがついているのかを調べるのもおすすめです。
たとえば教科書、文房具、筆箱、ランドセル、鍵盤ハーモニカやリコーダー、体操服など、よく使うもののリサイクルマークを調べてみましょう。
リサイクルマークの種類がわかったら、自分の住む地域のごみ収集・分別方法を調べてみてもよいですね。
たとえばプラスチック製品がどのような分別・回収をされていて、地域のどのごみ収集場に行き、どのような経路でリサイクルまで進んでいくのかをチャートにしてまとめてみるのです。
まとめ方はノート、プリント、新聞など好きな方法でOK。身近なものを扱う自由研究ですし、学校の勉強ともリンクさせやすいテーマなので、楽しんで取り組めるでしょう。
オリジナル楽器作り

image by:Shutterstock
2つ目のアイデアは、ペットボトルや木など、身近なものを使ったオリジナル楽器作りです。
本来は捨てるはずだった廃品を使って、オリジナル楽器を作ってみましょう!
オリジナル楽器作りのアイデアはYouTubeにもたくさん載っているので、参考にしてみるのがおすすめ。
まずは自分で設計図を作って作成し、「音が鳴らない」「思うような音が出ない」というときに、完成品と比較して問題点を改善していきます。
作成の流れをレポートにすると、興味深い自由研究ができるでしょう。
また、簡単な楽譜に合わせて、オリジナル楽器で演奏できるかどうかを検証してみるのもおすすめです。
複数の楽器の演奏をパートごとに動画で撮影し、後で合成して一曲にしてみてもよいでしょう。
パソコンを使って動画編集するのも、立派な自由研究になりますよ。
完成した動画は教室で流せるようSDカードに保存しておいたり、QRコードにして先生に頼み、流してもらってもよいのではないでしょうか。
ご近所防災マップ作り

image by:Shutterstock
3つ目のアイデアは、ご近所防災マップ作りです。
自宅や学校周辺の防災マップを手作りし、避難場所はどこなのか、避難ルートにどんな危険があるかなどを書いていきます。
自分自身や家族、さらにクラスメイトの防災意識も高められる自由研究ですよ。
ご近所防災マップを作るときは、実際に家の人と避難ルートを歩き、目で見て危険がないかを確認するのがポイント。
写真をマップに貼り付けたり、感じたことをこまめに書いたりすると、充実した防災マップができあがります。
日中は暑いので、涼しい時間帯に歩いたり、日傘をさしたり、こまめに水分補給をするなど、熱中症対策も忘れずに。
防災マップと一緒に、防災リュック作りなども自由研究として書いておくとよいかもしれませんね。
「この商品は近くのお店で揃えられたけど、これは遠くのホームセンターにしかなかった」とか「すべてを入れたリュックは◯kgあって、少し重い」など、実際に作ったときのコメントも添えておくのがおすすめです。
夏休み中に足が速くなるかチャレンジ!

image by:Shutterstock
4つ目のアイデアは、夏休みや冬休みの時間を使って、どれだけ足が速くなるかチャレンジすること。
夏休み初日のタイムと最終日のタイムを比べ、練習の成果が出たかどうかを表にしてまとめてみましょう。
チャレンジする際は、自分のフォームと、足が速い人のフォームを比較できるよう写真や動画を撮ってみるのがおすすめです。
写真を並べて貼り、最終日との変化を比べてみてもおもしろいですね。
どんな方法で挑戦してみるのかなど、参考にした動画や本があればしっかり記録しておきましょう。
実際にタイムが縮んだ場合、クラスメイトが参考にしてくれるかもしれません。
なお、1週間おきにタイムを計り効果が出なかったという場合は、ほかの方法にどんどん切り替えてみるのもおすすめです。
さまざまな方法を試したなかで一番効果のある方法がわかれば、クラスメイトにとっても有意義な自由研究になりますね!
夏休み新聞

image by:Shutterstock
5つ目のアイデアは、夏休みに起きたことを新聞にまとめる、夏休み新聞です。
身の回りで起きたおもしろいこと、出かけた先で学んだおもしろい情報などをギュッとまとめてみましょう。
新聞の構成は、実際の新聞を参考にしてみるのがおすすめです。新聞をとっていない家庭でも、コンビニで新聞がすぐに買えるので、ぜひ買ってみましょう。
新聞にどんなことが書かれているのかがわかれば、「大見出しには旅行の話を書こう」「小見出しには家の手伝いをした話」「コラムにはおもしろかったエピソード」など、自然と書く内容も決まってきます。
夏休み新聞の自由研究は、用意するものが少ないというメリットもあります。
大きな新聞を作るにしても、模造紙とペンは文房具屋ですぐに手に入りますよね。
写真を撮って印刷して貼れば、見ごたえのある夏休み新聞が低価格で作成できます。
地域によっては子ども新聞コンテストなども開催されているため、気になるテーマを決めて新聞づくりをしてみてもよいでしょう。
夏休みの自由研究にもなりますし、コンテストにも出せるので作り甲斐がありますよ!
タイムラプスで観察日記

image by:Shutterstock
6つ目のアイデアは、タイムラプスで観察日記をつけることです。
観察する対象は学校から持ち帰ってきた朝顔などの植物のほか、ミニトマトなどの野菜、昆虫などもおすすめですよ。
観察日記というと、絵に書くのが一般的な方法ですよね。しかしスマホやカメラが普及しているいまだからこそ、いつもとは違った方法で観察日記を作ってみるのもおすすめです。
タイムラプスをとるのが難しいという人も、1時間に1回写真を撮るようにして、あとでパラパラ漫画のようにつなげるだけでも成長の仕方が動画のように残せるでしょう。
学校で動画再生ができなかった場合に備え、1日ずつの写真をノートに貼り、一言ずつコメントを書いた日記を作っておくのも大切です。
一番飛ぶ紙飛行機づくり

image by:Shutterstock
7つ目のアイデアは、一番飛ぶ紙飛行機を作ることです。
紙飛行機の折り方はいろんな種類がありますし、なかには「よく飛ぶ!」と好評のものもあるでしょう。
はたしてどの折り方が一番飛ぶのか、夏休みの時間を使ってじっくり研究するというアイデアです。
使用する紙は1種類に絞り、飛ぶ場所は風の影響を受けにくい室内など、すべての紙飛行機が同じ環境下で飛ばせるようにするのがベスト。
飛ばすときのフォームについても研究しておけば、最も良い状態で紙飛行機ごとの実力を比較できるでしょう。
トーナメント形式で紙飛行機同士を競わせるのもおすすめです。
自由研究を見てくれる人も、ワクワクしながらトーナメントの結果を見守ってくれるに違いありません。
優勝した紙飛行機は、折り方を書いておくと、みんなが真似してくれそうですね!
昔の暮らしを調べて実践

image by:Shutterstock
8つ目のアイデアは、昔の暮らしを調べて実践してみることです。
家の人の協力が必要になってしまいますが、「洗濯機を使わずに洗濯してみる」「ご飯を土鍋で炊いてみる」「ほうきとちりとり、雑巾で掃除をする」など、昔実践されていた方法で日ごろの家事を行ってみましょう。
昔の食事を再現してみたり、昔の遊びで楽しんでみたりするのもおすすめです。
いまの暮らしと比較し、どんなところが便利になったのかを書き出してみましょう。
また「こんな暮らし方もいいじゃん!」と思ったら、そんな感想もどんどん書くのもいいかも。
比較するだけではなく、昔からいまにかけてどのような変化があり、どういう進化を経ていまの形になったのかを調べて書くのもよいでしょう。
携帯・テレビ・冷蔵庫・炊飯器・掃除機など、日ごろよく使っている家電の変化は、調べていておもしろいと感じられるはず。
周りの大人に「どんなものだったの?」と質問してみるのもよいかもしれませんね。
地域の特産品や伝統文化調査

image by:Shutterstock
9つ目のアイデアは、地域の特産品や伝統文化の調査です。
住み慣れた街が大事にしている特産品や伝統文化があるのなら、ぜひ深掘りして調べてみましょう!
地域によっては体験学習や工場見学ができる場合もあるので、積極的に参加したいもの。
実際に文化に携わっている人にインタビューしてみれば、ほかの人とは違うおもしろい自由研究ができあがるでしょう。
調査の際は、ぜひ発展の歴史や、世界でどのようなイメージを持たれているのか、観光にどんな風に役立っているのかなども調べてみるのがおすすめです。
地域の紹介パンフレットを作るような気持ちで、カラフルにわかりやすく作ってみてくださいね。
世界の小学生調べ

image by:Shutterstock
10個目のアイデアは、世界の小学生を調べることです。
世界中の同年代の子供たちに目を向け、どんな小学校生活を送っているのかを調べてみましょう。
その国ならではの学習スタイルが見つかったり、可愛い制服が発見できたり、日本との共通点が見つけられたりしそうですね。
また小学生に人気のキャラクターやゲーム、遊び、家で何をしているのかなども調べるのがおすすめ。
世界中の小学生の暮らしに密着しながら、自分だけの「世界の小学生地図」を作り上げると見ごたえバッチリです。
インターネットだけではなく、図書館に足を運ぶなど、調べ方もさまざまなので、いろんな方法で調査してみましょう!
- image by:Shutterstock
- ※掲載時の情報です。内容は変更になる可能性があります。
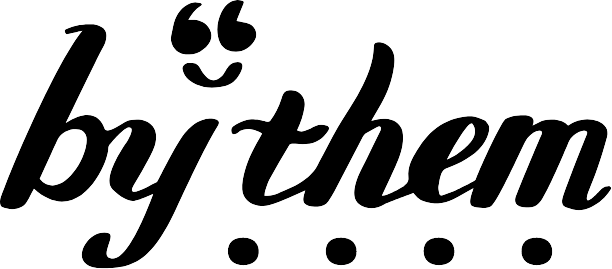

 3 件
3 件