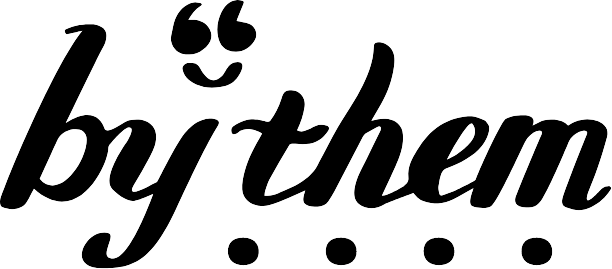20歳年上の夫と高校2年生のマイペース息子と暮らしている、主婦ライター・塩辛いか乃です。
昨年、息子とニューヨークへ二人旅をしてきました。
知らない場所が大嫌いな息子。ですがわたしは、チャンスがあれば息子に日本の外を見せたいと思っていました。
海外研修も控えていた息子。海外なんて怖いと騒ぐので、それならば一度一緒に行ってしまえば「こんなもんか」と思えるかも…と思い立ち、息子に聞いてみると「海外は怖いけど、ニューヨークならちょっと行ってみたい」と言い出しました。
彼が大好きな映画『スパイダーマン』はニューヨークが舞台。シリーズで何度も見ていて、視覚的になじみがあるのだそう。
学校の校外学習でさえ「怖い」とパニックになっていた息子が海外に興味を持つなんて、成長じゃないか。
とはいえこの物価高に円安で「いまですか?」と思いつつ、来年は受験、その次は大学生。もしかしたらいまがチャンスかもしれないと思い、決行することにしました。
息子の一声で決まったニューヨークは、わたしも未経験。もともと都会よりも遺跡などを見たいので、自分では選ばない旅行先。だからこそ楽しもうと思い、せっせと計画を立てました。
オクテで内気な息子、この機会に刺激を与えられるだけ与えたいと、張り切って観光予定を組む私。ブロードウェイミュージカルはもちろん、美術館に博物館に、ハーレムのゴスペルツアーなどあれこれセッティング。地下鉄を利用して街歩きもたくさんしました。
そんな「ザ・観光客」な旅ではありましたが、それでもニューヨークは「日本と違うなぁ」と思ったところがたくさんありました。
子どもを育ててから本格的な海外旅行は初めてで、若いころにバッグパッカーで旅行していたときには目につかなかったであろう、子持ち主婦ならではの気づきがたくさんありました。今回はそのことについてお話しします。
日本とアメリカの「地下鉄」の違い

image by:Framalicious/Shutterstock.com
わたしたちはマンハッタンの観光で、地下鉄を使いました。
以前は犯罪の温床だったという地下鉄に乗るのは正直怖かったのですが、いまは一般市民も普通に乗れるとのことでチャレンジ。それがとても新鮮な経験でした。
地下鉄のホーム自体がまだまだ古臭く、昔映画で見たまんまの状態。エアコンが効いておらず、蒸し暑くてちょっと嫌な臭いがする感じの場所。そこにゴゴゴゴーと轟音を立てて電車が到着します。それだけでもすごい音量。
観光地間の移動なので、車両に乗り込むとけっこう混んでいました。欧米人の観光客や地元の人っぽい若者グループなどなど。そして電車内ではまぁ楽しそうにワイワイ話す話す。
もちろんひとりで静かに座っている人もいますが、イヤホンで音楽を聴きながら鼻歌を歌っているご機嫌な男性もいます。
駅に到着すると、そのうるささにプラスして割れたマイク音で「〇〇駅~」とアナウンスが入ります。それがまた音量が大きい割に音が悪くて聞こえない…。
そんな乗客のなかには、赤ちゃん連れや小さい子連れの親子もいます。当然グズって大泣きしている子もいます。
ですがこの電車内があまりにうるさいせいか、別に気になりません。そして周りも一切気にしている様子はなし。たぶん結構なボリュームで泣き叫んでいるんですけどね。
さらにその次の駅で、足が悪いようで杖をついた中年女性が乗ってきました。するとイヤホンで音楽を聴いてノリノリだった男性が、ものすごい素早さで立って席を譲っていました。
たしか目をつむって曲に聞き入っていたような気がしたんだけど…そしてぱっと見はなかなかイカツイ雰囲気の男性…いや、人は見た目によらないけれど、スマートな身のこなしに正直びっくりしました。
「海外では体の不自由な人や老人に席を譲るのが当然なので優先席がない」と聞きましたが、ニューヨークの地下鉄車内も、優先席っぽいものは見当たらず。
ほんの少し色の違うあったので、もしかしたらそれかもしれませんが、そもそも足の悪い方やご老人が乗ってきたら誰かがすかさず譲るので、優先席が必要ないというのは本当だなと思いました。ニューヨーク滞在中、席を譲る人を何回も見ましたよ。
そんな地下鉄内の様子を見て、日本と違ってすごく居心地がいいなぁと感じてしまった私。
日本では、電車内は静かにするのがマナー。イヤホンの音漏れでさえ嫌な顔をされ、それがもとでお客さん同士のトラブルになったりします。
友達同士で電車に乗ったら、複数人いれば声も大きくなりがちですが、そんなに大きな声で話す人はいません。学生でもやりません。
そして赤ちゃんが泣けば、お母さんは犯罪者のように肩身の狭い思いをして必死で「静かにして!」と泣き止ませようとし、周りはなんとなーく白い目を向ける。お互い居心地が悪いですよね。
そして誰かがコホンと咳をしようものなら白い目で見られる(ような気がする)。イヤホンで鼻歌なんて言語道断でしょう。
そして優先席が空いていても座っていることもなんだか後ろめたい。疲れてきょうは譲れないよと思って座っていると、なんとなく譲らないことを責められているような気がして寝たふりをする。
思い切って席を譲ると「次で降りますから結構です」とか断られたりもする。そんな経験、みんなあるんじゃないでしょうか。
日本の電車は静かでいいのですが、マナーが行き届きすぎていて、その割に席を譲らないと「譲れよの圧」を感じてしまい、わたしは日本の電車に乗るとき、とても窮屈な気持ちになります。
それに、静かすぎて、子どものはしゃぎ声が気になってしまいます。それに伴うママの「静かにして!」という肩身の狭そうな雰囲気も…。
ニューヨークの地下鉄はそういうのが全くなくて、うるささには辟易しつつも「なんかラクそう」と思いながら利用していました。
静かに座っている人も、その喧騒を迷惑そうにしておらず、本を読んだりしている。みんなが他人を見張るということをしておらず、自分たちの時間を楽しんでいる雰囲気でした。
科学や芸術への価値観や興味

image by:Steve Rosenbach/Shutterstock.com
地下鉄に乗って、美術館や博物館を訪れましたが、そこで特に驚いたのは、美術館に子連れ客の多いこと。
わたしはメトロポリタン美術館(MET)とMoMA(ニューヨーク近代美術館)を訪れましたが、特にメトロポリタン美術館は子どもがたくさん。
日本の美術館は、ものすごく静かですよね。おしゃべりすると叱られるし、フムフムという顔をしながら静かに絵画を鑑賞すべしというような雰囲気が満点。
けれどメトロポリタン美術館は、美術館内自体がザワザワしています。
広大な建物のなかに膨大な数の展示がされ、絵画だけでなく、エジプトやギリシャの彫刻や神殿まで見ることができるのですが、お客さんはそれを見ながら何やら語り合ったりしているし、フラッシュをたかなければ写真撮影もOKなので写真を撮りあったり。
ミイラを見て「わお」と言っていたり。ベビーカーを押した家族がいたり、幼稚園から小学校くらいの子どもと一緒に絵画を見ている人も割と多いのです。
日本では、美術館って「大人の高尚な趣味」のようなジャンルにあると思うのですが、ニューヨークでは小さいころからこういう世界のアートや歴史に触れているのかと思うと、育まれる価値観が変わるのだろうなと思います。日本はアートやエンタテインメントへの評価が低いと言われますが、なんとなく納得してしまいました。
さらに博物館。息子が科学博物館が好きなので自然史博物館を訪れましたが、こちらは夏休みということもあり、子連れがたくさん。これでもかというほど大量の恐竜の化石骨格や、アメリカや世界中に住む動物の展示など、こちらも見ごたえ抜群。子どもたちもどのエリアでも楽しそうに見学しています。
そして展示の仕方も、ものすごく工夫されていてとてもおもしろいのです。
たとえば動物コーナーでは、各動物の剥製がジオラマ展示されています。そしてその周りの環境、たとえばその動物が住んでいる場所に生えている木や草花、生息している小動物までしっかり再現されています。
高地に住む動物であれば背景は高山で、後ろにはコンドルが飛んでいたりします。群れを成す動物は、群れで表現。肉食動物は捕食の瞬間をとらえて剥製で再現しています。
周りに生えている草花まで緻密に再現され、その動物を見るだけで、どんなところに住んでいるのか、暑いところなのか、高いところなのか、草原なのか一瞬でインプットされます。
夜行性のフクロウやオオカミなんかは展示の部屋自体が真っ暗。「あ、夜行性なんだな」と一瞬でわかります。
さらに、昆虫コーナーでは生体展示が豊富。「ハキリアリ」という、特定の歯をちぎって巣の材料にする行動特性を持つアリの展示は見事でした。
巣作りの元になる葉のある場所と、巣づくりの場所を透明のパイプでつなぎ、どうやってハキリアリが歯をちぎり、それをどこに貯めて、どう加工していくかがすべて見えるようになっていました。
大人も子どももアリの行動を見守って、ときが過ぎるのを忘れてしまいます。
小さいころからこんな博物館に来ていたら、興味も自然と湧いてきそう。しかもニューヨーク在住であれば、博物館も美術館も入館無料だとか。太っ腹!
ちなみに、日本の国立科学博物館には息子が小さいころからよく行っていました。日本で一番大きな博物館ですし、その展示は工夫されているとは思いますが、このニューヨークの博物館のすごさを見てしまうと「日本頑張れ!」と思ってしまいます。
先日、国立科学博物館は予算不足でクラウドファンディングまでしていたことを考えると、国からの予算がついていないのでしょう。アメリカの博物館のような展示をつくり、それを維持するには相当お金がかかるであろうことは、シロウトのわたしでもわかります。
財団からの寄付による展示も多く、この博物館を素晴らしいものにするためにアメリカの財力が集結しているんだなと感じました。
日本はこういった科学技術にも予算を使わないと言われていて、そういった面がこの美術館や博物館の規模や展示に現れているのかなぁと思ってしまいました。
優秀な日本人はたくさんいるけれど、日本は研究費があまり出ず、思い切り研究したいと思えば海外に行くしかないとも聞いたことがあります。ノーベル賞を受賞した日本人なんかも、海外大学にいますよね。
そういう意味でも、科学や芸術への価値観や興味が国によって違うのかなと感じました。
ニューヨーク州はアーティストを保護する法律もあるそうで、アートを飾ると補助金が出たりと、さすがアートとカルチャーの中心地と言われるだけあるなという施策があったり、街中にもたくさん美術館があったり、街にパブリックアートが点在していたりします。
日本では、博物館や美術館に行くことは少し敷居の高い行為に感じられますが、ニューヨークでは市民に浸透しているような雰囲気がありました。この雰囲気の違いで、育つ人材が変わってくるんだろうなぁと感じさせる何か。
数日間の滞在でしたが、そんな「ニューヨークという風土」を感じることができた旅でした。
もしかしたら実際に住むと全く違う感じ方をするかもしれませんし、どちらがいいという話でもありません。
ただ、人種も民族も多様なニューヨークという街が、単一民族で長くやってきた日本とは大きく違う文化や価値観を持っているのだなという体験はとても刺激的でしたし、息子にもよい刺激になったと思います。
そんな感想を抱きつつ日本に戻ると、また違った視点で日本が見えてくる気がします。
- image by:Mulevich/Shutterstock.com
- ※掲載時の情報です。内容は変更になる可能性があります。
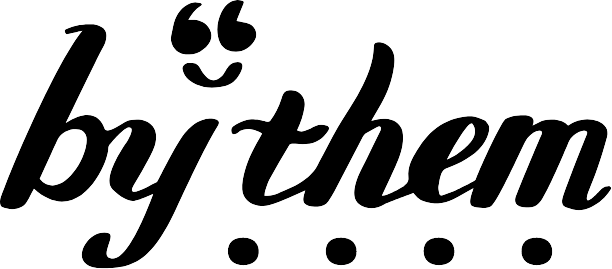

 5 件
5 件