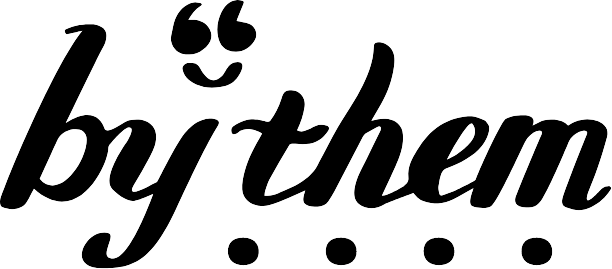共に生きる皆さんへ。こんにちは、野澤卓央です。
頭の声と、心と身体の声。
「“心身の声”を聴きたいけれど、“頭の声”との違いがわからないんです」
そんな相談をいただきました。
お話を聴いていくと、その方はこう言いました。
「今、正直すごく疲れているんです。でも“休んでいる場合じゃない”。休んだら大変なことになる気がして…」
ここには、ふたつの声が同時に存在しています。
心身の声を聴き、いのちを育むコツ

image by:Unsplash
ひとつは、心と身体の声。「疲れている」「休みたい」と伝えてきています。これは、“心身の望み”です。
もうひとつは、頭の声(思考)です。「今は休んでいる場合じゃない」「休んだら大変なことになる」と、休むことを否定します。
このふたつの声の関係を、親子関係に喩えることができます。
たとえば、子ども(心身の声)が「疲れたよ、休みたい」とつぶやいたとき、すぐ隣で親(思考の声)が「何言ってるの、休んだらダメでしょ。そんなことしたら大変なことになるわよ」と、きつくたしなめてしまうような。
思考の声に乗っ取られると、私たちは四六時中、厳しい親につきまとわれているような状態になります。
「これは正しい」「常識的にこうすべき」「こうしないとダメ」といったような“正解”を押しつけられ、本当の心や身体の声は聴いてもらえずに疲弊していくのです。
「親」という字は、「木の上に立って見る」と書きます。
本来の親の役割は、子どもの声をよく聴き、見守り、必要なときにだけ手を差し伸べること。
それと同じように、私たちが自分の心身の声を丁寧に聴き、見守り、必要に応じて思考がサポートをしてあげられたら、私たち自身の“いのち”も、健やかに育まれていきます。
さきほどの例でいえば、「休んだら大変なことになる」という思考の裏には、不安や恐れが潜んでいます。
その不安や恐れ自体も、無視せずにそっと寄り添う。そんな知性が、私たちの中にはきちんと育っていくと思っています。
さらに、自分の心身の声を聴き、理解し、支えられる人は、子育てや人のマネジメントも自然とうまくいくと僕は感じています。
なぜなら、真のマネジメントは「セルフマネジメント」から育まれるものだからです。
私たちは、赤ちゃんのころに“健全な衝動”があり、その衝動が安心できる関係性のなかで受け止められることで、“健全な情緒、感情”が育ちます。
そしてその土台の上に初めて“健全な知性”が芽生えていきます。
健全な知性とは、自分や他者を責めたりコントロールするためのものではなく、「今、何が起きているのか」「どうすれば支え合えるのか」と、理解し寄り添う力で、つまり、そこには“慈愛”や“慈悲”が生まれていきます。
自分だと思っている「私」それは、多くの場合“自我”と呼ばれる存在です。この自我は、2歳前後から発達する心の器官であり、目や耳と同じように、生きるために必要な機能のひとつです。
本来、自我の役割は、「いのちを守る」「生きる方法を考える」ためにある、道具のようなものです。
でもその“道具”であるはずの自我が、まるで自分が主人公であるかのようにふるまい、身体や心の声を聴かずに、自分勝手に指示を出しはじめたら、当然、身体も心も不調和を起こし、やがては自我自身も苦しみ始めます。
けれど実は、私たちには「自我が生まれる前の私」も、ずっと存在してきました。
それが、“いのちとしての私”です。
心身が整い、静かな平安に包まれるとき、思考や自我の声は自然と静まります。
そしてそのとき、自我は本来の役割を思い出し、自他を慈しみ育む存在へと変わっていくのだと思います。
13年間、みんなの学校(旧コツ塾)や研修などを通して、延べ数千に出逢い、歩む中で、智慧を得て、実践することで、人は何歳になっても土台から立て直すことができると僕は確信しています。
土台から地に足ついて歩むことに、可能性を感じる方、興味がある方は、お話会やセミナーなどがあるとき、一度、参加してみられてください。
自分を救い、育むだけでなく、お子さんを想う親御さん、教育者、リーダーにもおすすめです。
今日も、生きとし生けるものすべてが平和で幸せでありますように。
【今日のコツ】
自分を理解することが、自他を健全に育むことの始まり。
- image by:Unsplash
- ※掲載時の情報です。内容は変更になる可能性があります。
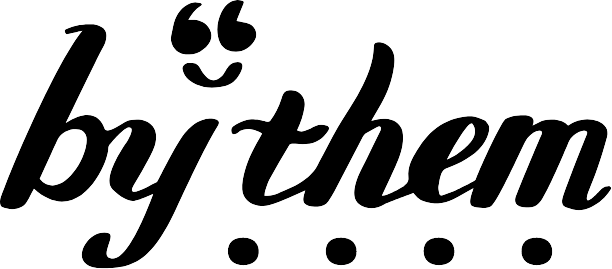

 0 件
0 件