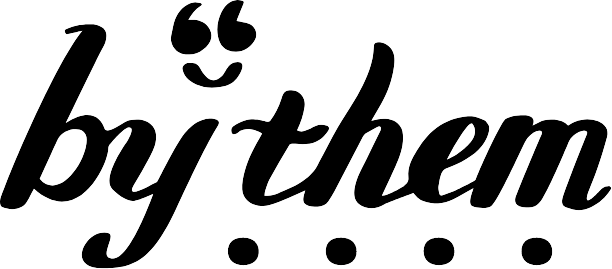近年、日常的に使用される柔軟剤の香りが、意外な健康被害を引き起こしているという問題が注目を集めています。X(旧Twitter)でもトレンドに上がっていました。
特に、子どもたちの学校生活において、この「香害」と呼ばれる現象が深刻化しており、最新の調査結果がその実態を明らかにしています。
小中学校で起きている「香害」の現状とは

image by:Shutterstock.com
柔軟剤に含まれる人工化学物質が原因で、小中学生の約1割が頭痛や吐き気などの体調不良を経験しているそうです。
コロナ禍になってから二重のマスクで対応し始めてから、そんなに気にはならなくなっていましたが、確かに柔軟剤のニオイはキツイ。施術していても「クラ~」っとくる瞬間も少なからずありました。
本当に柔軟剤の香りがもたらす健康リスクというものがあるのでしょうか?今回はこのあたりを詳しく掘り下げてみたいと思います。
調査の背景や症状の詳細、さらには家庭や学校での対策まで。まずは、なぜ柔軟剤の香りが「害」となるのか、そのメカニズムから追ってみましょう。
柔軟剤は、洗濯後の衣類を柔らかくし、心地よい香りを付与する製品として広く普及しています。しかし、その香りの源泉は、主に合成された人工化学物質。怖いねー。
これらの物質は、揮発性が高く、空気中に広がりやすい性質を持っていて、閉鎖的な空間である教室では特に問題となることでしょう。
東京新聞の報道によると、衣料品の洗剤や柔軟剤に含まれる香料の人工化学物質が、子どもたちの心身に悪影響を及ぼしていることが明らかになったそうです。東京新聞はとりあえずいいね。
具体的には、これらの化学物質が皮膚や呼吸器を通じて体内に取り込まれ、過敏症を引き起こすケースが増えているのだそう。
環境省や専門家によると、こうした物質はマイクロカプセル化されて衣類に付着し、長時間にわたって香りを放出するため、周囲の人々への影響が持続的になるといいます。

image by:Shutterstock.com
たとえば、教室で30~40人の子どもたちが柔軟剤を使った衣類を着用している場合、授業終了時にはその香りが互いの服や髪、鞄にまで移り、避けられない暴露状態が生じるというのだから、クラクラしたって不思議ではありません。
この問題を科学的に裏付けるのが、2024年〜2025年にかけて実施された大規模調査。
日本臨床環境医学会の環境過敏症分科会と室内環境学会が共同で、全国9都道府県の21自治体を対象に、約1万71人の保護者から回答を集めました。
調査結果は衝撃的で、小中学生の10.1%が、学校で柔軟剤由来の香りによる体調不良を経験したと報告されていました。
さらに、幼稚園児や保育園児を含めると8.3%に及び、被害者のうち25%(4人に1人)が登校や登園を渋る傾向を示したのです。

image by:Shutterstock.com
症状の詳細を見てみましょう。
主なものは頭痛、吐き気、腹痛、下痢、関節痛、目のかゆみや充血、皮膚の発疹など多岐にわたります。
これらは化学物質過敏症の典型的な兆候で、特に子どもたちは免疫系が未熟なため、大人よりも敏感に反応しやすいと言われているのです。
調査では、学年が上がるにつれて被害率が高まる傾向が見られ、小学校高学年や中学生で10%を超えるケースが確認されました。
これは、思春期のホルモンバランスの変化や、ストレスが増える学校環境が影響している可能性があります。
実際の被害者の声も、心を痛めるものです。
ある母親は、「教室に30~40人の子どもたちが柔軟剤の香りをまとって集まると、帰宅時にはその匂いが服や髪、鞄にまで移ってしまいます。子どもの苦しみを認めてほしい」と訴えています。
別のケースでは、1年生の男の子が香害で学校に行けなくなり、母子ともに外出時にガスマスクを着用せざるを得ない状況に追い込まれたというのですから、世も末。
これらの事例は、柔軟剤の香りが単なる「好みの問題」ではなく、深刻な健康被害を引き起こすことを示している。
また、学校の共有物、例えば体操服や掃除道具が香り付きの洗剤で洗われる場合、個人の努力だけでは防ぎきれない点が課題に。
明治大学名誉教授の寺田良雄氏は、「体調不良に至らないまでも、多くの子どもたちが不快を感じている」と指摘し、学習環境全体が香害によって損なわれていると警鐘を鳴らしているのであります。
この香害の問題は、柔軟剤だけでなく、洗剤や整髪料、香水などの他の製品とも関連しますが、東京新聞の報道では、特に柔軟剤と洗剤の香料に焦点を当て、正確に事実を伝えている点が特徴でした。
一方、他のメディアでは整髪料や香水に重きを置く場合もありますが、調査の本質は衣類から放出される持続的な化学物質にあると言えるでしょう。
歴史的に見て、柔軟剤の香り強化は2000年代以降のマーケティング戦略によるもので、以前は無香料が主流でした。しかし、消費者の「良い香り」志向が高まる中、健康被害の報告が増加。
消費者団体「香害をなくす連絡会」や超党派の「香害をなくす議員の会」は、文部科学省に対し、全国規模の調査と学校での啓発活動を要望しています。
では、僕らはどう対処すべきなのでしょうか。
子どもたちの健康を守るため、私たちがすべきこと

image by:Shutterstock.com
まず、家庭レベルでは、無香料または低刺激性の柔軟剤を選ぶことが有効でしょう。
成分表示を確認し、合成香料を避け、自然由来のものを優先する。また、学校では、保護者会を通じて香害の啓発を行い、体操服の洗濯ガイドラインを設けることが考えられます。
専門家は、教室の換気を強化したり、香りの強い製品の使用を控えるルールを導入したりすることを推奨しています。
さらに、社会全体として、製品メーカーに化学物質の規制を求める声が高まっていて、環境省も、化学物質過敏症のガイドラインを策定中ですが、子どもたちの未来を守るため、早急な対策が必要なのはいうまでもありません。
このように、柔軟剤の香りは一見心地よいものですが、隠れたリスクを伴っています。
調査結果を踏まえ、僕ら一人ひとりが意識を変えることで、子どもたちの健康を守れるはず…なのかな。
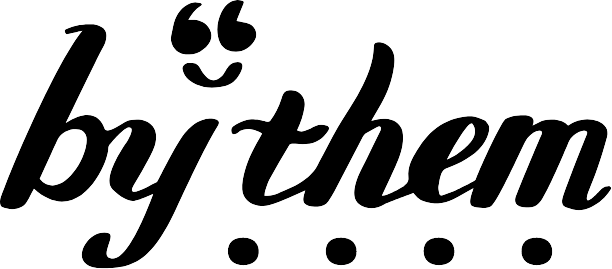

 3 件
3 件