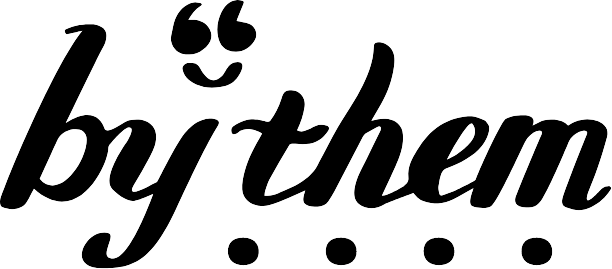考え方を変えて違った視点で見ると気持ちが楽になる

image by:Unsplash
認知症が進行すると、いままで当たり前にできていたことがだんだんとできなくなってきます。
私の母もお金の管理ができない、ついさっき言ったことを忘れてしまう、すぐにものをなくす…自分の身の回りのことが徐々にできなくなってきました。
また、それと同時に収集癖が酷くなったり、夏なのに真冬の格好をしたりと少し常識とかけ離れた行動をするようにも…。
その状態を側で見ていた私は、母の行動を否定したり、常識とかけ離れた行動をとがめて正したいと必死になっていました。しかし、必死になればなるほど疲れてしまうのです。
そこで、ある認知症介護者の方の話を聞いて考え方を変えることにしました。その考えとは、「介護する側の考え方を変えたら気持ちが楽になった」という内容でした。
「できない」ではなく「まだできることがある」
認知症が進行し、できなくなることは多くなりますが、「それは病気だから仕方ない。でも、まだできることもたくさんあるのだ。それは嬉しいことではないか」と発想を変えてみる。すると、気持ちが少し楽になってきたのです。
認知症が進行し、何度も同じものを買ってくる母でしたが、「まだ一人でお金を払って買い物することはできる」「自分のほしいと思うものは買うことができる」など何気なく母の行動を見ていると「まだできること」は、たくさんあります。
いずれは、自分の名前も、私のことも忘れてしまう日が来るかもしれない。でも「いまはこんなにできることがあるのだ」と考えるようにしたのです。
介護で余裕がないと、イライラしがちですが、認知症になった家族の行動を違った視点で見ることで気持ちが少し楽になるかもしれません。
できないことは多くなるが、印象深かった出来事の記憶はまだまだ残っている
認知症になるといずれ、何もわからなくなるだろう…。
しかし、認知症の症状が進行しても、印象深かった出来事の記憶や感情はかなり末期まで残っていると言われています。
特に本人が生活でずっと続けていたようなことや誇りをもってやってきたことなどは、身体が自然に動くほど本人にしみついているそうです。
私はNHKで放送された『認知症の母と脳科学者の私』という番組を見て、このことに気づかされました。
番組では、脳科学者の恩蔵絢子さんが認知症のお母さまと向き合う様子が放送されていました。その番組のなかで、とても興味深い場面がありました。
ピアノ講師をしていたお母さまは、自分の名前も言えないほど認知症が進行していたにもかかわらず、「まっかな秋」を歌ったときにきちんと歌詞をつけて歌うことができたのです。さらに、音楽の世界で鍛えてきた人でなければ出せない発声や表現をしていました。
私はこの番組を見て「認知症が進行しても脳の内部に積み重なったことは残っている」ということを初めて知りました。
そして、「母が昔得意だったことは、いまもまだできるのだろうか?」と思ったのです。
母は、昔押し花講師をしていて、絵を書くことや手芸などは得意でした。押し花講師を辞めてから数年は経っていましたが、母にそのときのセンスや感覚などは残っているのか確かめてみたくなりました。
ある日、母が私の子どもと一緒にお絵かきをしていたときのこと。「ばあば、富士山書いてみて」と子どもが言いました。母は、「いいよ」と言い、絵を描き始めました。
母が描いた絵を見て私の子どもは「わ~、きれい、ばあばは絵が上手だね」と言ったのです。
その言葉を聞いて、私は母の絵を見ました。驚くことに母は、押し花講師をしていたときと同じくらい素敵な絵を描くことができていました。
そして富士山とともにお花畑が描かれていた絵は、母がかつて押し花講師をしていた時に作成した作品によく似ていました。
認知症が進行し、ほんの少し前のできごとがわからなくなっても、認知症の人がこれまでの生活のなかで楽しんで取り組んできたことや誇りをもってやったきたことなどは、まだ体が覚えていると実感する瞬間でした。
そして、「できないこと」だけに目を向けるのではなく、「得意だったことや誇りをもって取り組んできたことは、まだできるのだ」と違う視点で接することも大切ではないかと思ったのです。
また、日々の介護のなかでは難しいかもしれませんが、認知症の人が得意だったことや楽しんで取り組んできたことを発揮できる環境づくりも大切なことなのかもしれません。
そのようなことを行える環境は、認知症の人にとって自信につながり、その姿を見る家族にとっても嬉しいことではないでしょうか。
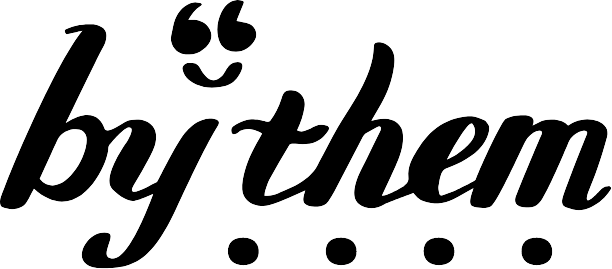

 7 件
7 件