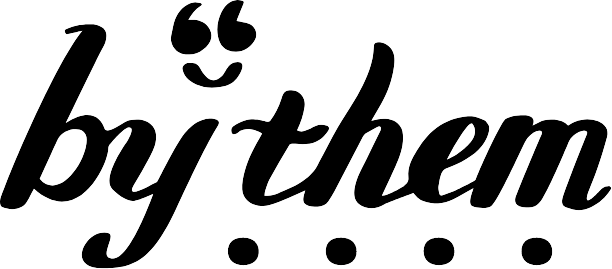自分の人生は自分の選択。「女は20代まで」はもう古い

image by:Unsplash
このようなステレオタイプをもつことは、ジェンダーギャップ指数世界156カ国中120位の日本の男性優位社会をさらに強めることにつながるのではないでしょうか。
実際に、菅義偉首相を含む菅内閣の閣僚の平均年齢は60.38歳という数字が出ており、さらに女性閣僚は21人中たったの2人しかいません(参考:日経新聞)。日本の男性優位社会を物語っているようにも見えます。
そして、元東京オリンピック・パラリンピック組織委員会会長の森喜朗の女性軽視発言が問題となった2021年2月。
「私どもの組織委員会に女性は7人くらいか。7人くらいおりますが、みなさん、わきまえておられて」と発言。さらに、ある議員秘書について「女性というには、あまりにもお年だ」と言及しました。
まさに「女は20代まで」といったステレオタイプが象徴する発言ではないでしょうか。「男性というには、あまりにもお年だ」と、男性に年齢を重ねることはあまり聞きませんが、女性に対して年齢や容姿を重視する人はいまだに存在しているのですね。
また、「独身30代女性=何か問題を抱えていて結婚、出産をしていない」とネガティブに捉えられる傾向もあると感じています。
女性が働く機会が増えたことや、育児コストを考慮したうえで、結婚や出産が「できない」のではなく「しない」女性は増えています。価値観やライフスタイルが多様化しているなかで、男性、女性ともに自分の人生を自分で選択する時代へとなりました。そんな時代で、森氏のような女性軽視発言は果たしてできるのでしょうか。
わきまえない女たちの登場

image by:Unsplash
森氏の問題発言を受け、Twitter上では「#わきまえない女」とハッシュタグを利用した投稿が、いまもなお広まっています。「女性はわきまえるべき」や「女性は男性を立てるべき」といった考えは、科学的根拠のないジェンダーに基づいたステレオタイプです。
そもそも「わきまえる」とは、物事の道理をよく知っているという意味。日本では、上司や社長、先輩とお話をする際、上の人に話を合わせる傾向があるように感じます。
そんな同調圧力のある環境で、違和感や意見を口にすることは難しいのではないでしょうか。管理的従事者に占める女性の割合が14.8%である日本(参考:第5次男女共同参画基本計画説明資料)。決めごとを行う会議や委員会の出席者はほとんどが男性であることは想像できます。
となると、男性がたくさんいる場で女性が声をあげない構造は、必然的に浮き彫りとなってしまうのです。
会社という大きなシステムに入ると、当事者である女性ですらも問題として受け取らないケースが多いです。実際に、「何か発したくても相手の意見に従うことのほうが、対立が起きずに楽でいられる」という社会人女性の声を耳にしたことがあります。
わきまえることが前提にある社会。そういった社会を問題視し、逆境に立ち向かう「わきまえない女たち」が声を上げてきています。
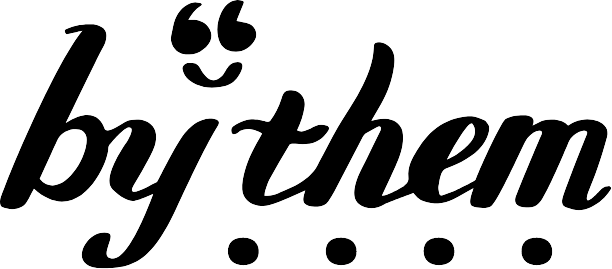

 13 件
13 件