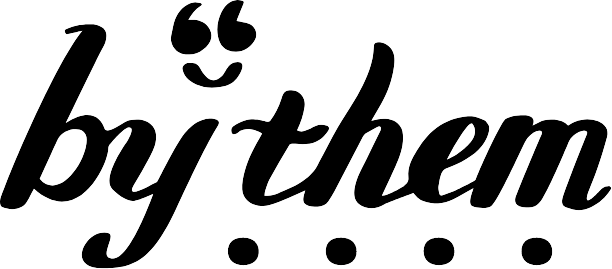「女は20代まで」そんな言葉を聞いたことはありませんか?残念ながら、令和のいまでも「30代に突入した女性は賞味期限切れ」という人や、「独身女性は余り物」と認識する人もいるようです。
さまざまな情報と触れ合うことで多様化が進むいま。100人いたら100通りの生き方があるのも当然です。しかし、いままでに浸透してきた「〜であるべき」の呪文により、多種多様な個がひとつの枠組みとして集約されているように感じます。
そして規範の枠組みからはみ出すことで、生きづらさを感じる人は多いでしょう。
社会に疑問の目を向ける若者たち

image by:Unsplash
インターネットの普及により、さまざまな情報に簡単にアクセスできるようになりました。スマートフォンひとつで、日本国内だけでなく海外の情報も取り入れることができたり、YouTubeなどの無料コンテンツが無制限に見ることができる時代。
日常で新しいことに触れられる時代を過ごす若者の価値観は多様化し、あらゆる選択肢が蔓延しています。異なる価値観を持つことが当然な時代だからこそ、いままでに構築されてきた規範的な社会に違和感を持つ人もいるでしょう。
いままでの社会を構築したのは、その時代を過ごしてきた大人たちです。また、その大人たちが属する会社には、社会を動かすような特権も付属します。多様な価値観を持つことが当たり前である若者と、規範的な社会を構築してきた大人たちが社内など同じ環境にいるとき、いまの社会を問題視するのは前者であると思います。
実際、多くの10代から20代の若者は、人権やジェンダー、セクシュアリティなどの社会問題に声をあげています。SNS上での情報共有や署名、ハッシュタグを使ったデモ活動など、現代ならではの方法で発信している若者も多く見受けられます。
さまざまな価値観をもつことが当たり前な環境にいるからこそ、自分だけでなく誰もが生きやすい社会を願って、声をあげているのではないでしょうか。では、そのなかでもいままで見過ごされてきた「女性の権利」はどうでしょうか。
広告が与える無意識の先入観

image by:Unsplash
毎日のようにスマートフォンを片手にSNSをチェックする時代へとなりました。そういったなかで必ず目にするのは、広告です。
動画を見るときも、記事を読むときも広告が出てきます。人々の目に映る広告の作り手である企業や大人たちは、若者たちのもつ生の声や多様な価値観に触れることが求められています。
たとえば、家事をする女性と仕事をする男性や、男性社長と女性秘書などの男女の役割は、広告を通して人々の思考に構築されてくと考えられます。実際に、仕事をする女性に家事をする男性、女性社長に男性秘書も存在しますが、広告によってないものとして打ち消されてしまうのです。
昔から存在する「女/男は〜である」というステレオタイプを、価値観が多様化する現代に流し込むことで、さらにステレオタイプを強化することにつながります。それだけでなく、規範の枠組みに当てはまらない人たちが、排除されてしまうことも十分にありえるのです。
アメリカ規格協会(ASA)の調査によると、「広告における性別のステレオタイプの描写は、性別の不平等を助長するだけでなく、子どもから大人まで、あらゆる人の選択肢や野心、機会を狭める」と示唆されています。
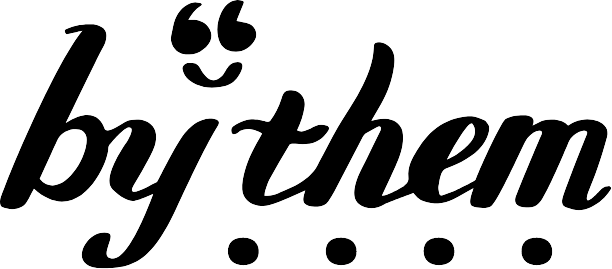

 13 件
13 件